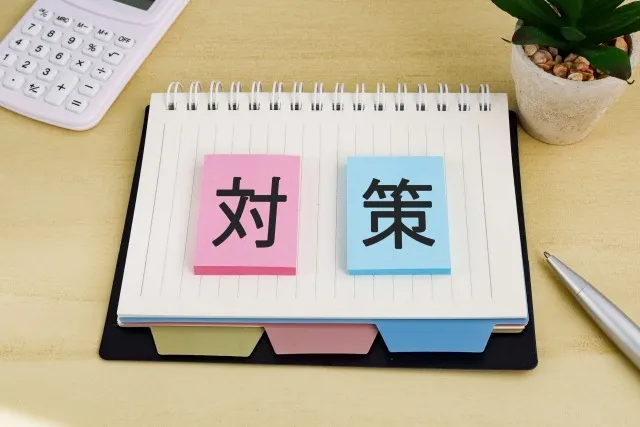脳梗塞の原因と症状を解説
2025/03/14
脳梗塞は生命に深く関わる重大な病気です。 本コラムでは、脳梗塞の原因や症状、治療法について説明します。また、退院後の生活では、生活習慣の改善と適切なリハビリが不可欠です。自宅でも安心してリハビリや健康管理を続けることができ、利用者様やご家族の負担を軽減するために、訪問看護が身近に寄り添い、個々に合わせたケアを提供することができます。
1. 脳梗塞とは?
脳梗塞は、脳の血管が詰まり、血流が途絶えることで脳の一部がダメージを受ける病気です。脳は酸素や栄養を血液から受け取ることで正常に機能しますが、血管が詰まるとその部分の神経細胞が死んでしまいます。これにより、体の麻痺や言語障害など、さまざまな症状が引き起こされます。 脳梗塞の主な原因には、動脈硬化、血栓(血のかたまり)、心房細動(不整脈の一種)などがあります。特に、高血圧、糖尿病、脂質異常症(高コレステロール)、喫煙、運動不足といった生活習慣が大きく影響します。
2. 脳梗塞の症状
脳梗塞の症状は、脳のどの部位がダメージを受けたかによって異なりますが、一般的に以下のような症状が見られます。
・片側の手足や顔の麻痺
・言葉がうまく出てこない、話が理解できない
・片方の目が見えにくい、視野が狭くなる
・強いめまいやふらつき
・意識障害
★緊急を要する症状:すぐに救急車を呼ぶべきサイン
脳梗塞は時間との勝負です。できるだけ早く治療を開始することで後遺症を最小限に抑えることができます。以下の症状が現れたら、すぐに119番通報し、救急車を呼びましょう。
FASTチェック という簡単な方法で脳梗塞の疑いを確認できます。
・Face(顔):笑顔を作らせたときに片側が下がっているか?
・Arm(腕):両腕を上げさせたときに片方が下がるか?
・Speech(言葉):言葉が不明瞭になったり、理解できない言葉を話すか?
・Time(時間):上記が一つでも当てはまれば、すぐに救急車を呼ぶ。
BE-FAST
・B(バランス):ふらつき
・E(目):視野障害
★視覚症状も注意すべきポイントとして知られている
一時的な視界欠損や目のかすみ、視界の一部が欠けるなどの症状も、脳梗塞の前兆である可能性があるといわれています。目の症状が数分〜数十分で回復しても、すぐに医療機関を受診することが重要です。
また、一過性の症状でも脳梗塞の前兆である可能性があるため、タクシーでの受診ではなく、緊急車の利用「救急外来」を推奨します。通常の外来受診では、他覚的にわかりにくい症状の場合、待ち時間が長く適切な処置が遅れ後遺症の発症に繋がることがあります。そのため迷わず救急を利用しましょう。
3. 脳梗塞の治療方法
脳梗塞の治療には、発症直後の「急性期治療」と、その後の「回復期治療」「維持期治療」があります。
・血栓溶解療法(t-PA):発症から4.5時間以内に投与すると、血栓を溶かして血流を回復できます。
・カテーテル治療:太ももの血管からカテーテルを挿入し、詰まった血栓を取り除く手術。
・リハビリ治療:脳のダメージを受けていない部分を鍛え、機能を回復させる。
・薬物療法:血液をサラサラにする薬、血圧をコントロールする薬など。
4. 脳梗塞の後遺症とリハビリ
脳梗塞の後遺症は個人差がありますが、主に以下のようなものがあります。
・片麻痺(半身の麻痺)
・言語障害(話す・理解することが困難)
・嚥下障害(飲み込む力の低下)
・認知機能の低下
これらの後遺症を軽減するためには、リハビリが重要です。理学療法(歩行訓練)、作業療法(手の動きの改善)、言語療法(話す・飲み込む訓練)などを組み合わせて行います。
5. 退院後の生活と注意点
脳梗塞を発症した方は、再発のリスクが高いため、退院後の生活がとても重要になります。
・食生活の見直し:塩分・脂質を控え、野菜を多く摂る。水分をしっかり摂る。
・運動習慣をつける:無理のない範囲でウォーキングや体操を行う。
・服薬の継続:血圧や血糖値を管理するための薬をしっかり服用する。
・ストレス管理:リラックスできる時間を作る。
6. 訪問看護によるサポート
脳梗塞を経験された方の中には、退院後も自宅でのケアが必要な方が多くいます。
訪問看護では、以下のようなサポートを提供できます。
*健康管理(血圧・体温・脈拍測定)
・血圧や体温の変化を定期的に確認し、異常があれば医師に報告。
・脳梗塞の再発リスクを軽減するための健康管理。
*服薬管理(飲み忘れ防止、薬の調整)
・服薬スケジュールの管理や、正しい飲み方の指導。
・副作用のチェックや、薬の変更が必要な場合の医師との連携。
*リハビリ支援(歩行訓練、日常動作の訓練)
・筋力低下を防ぐためのストレッチやリハビリ。
・生活に必要な動作(食事・着替え・移動)のサポートとトレーニング。
*嚥下訓練(誤嚥予防の指導)
・飲み込みのリハビリを行い、誤嚥性肺炎を防ぐ。
・食事の形態や食べ方の工夫についてアドバイス。
*家族への介護アドバイス(介護負担を軽減する方法の提案)
・家庭での介護負担を減らすための工夫やアドバイス。
・家族が無理なく介護できるように、福祉サービスの活用方法を紹介。
訪問看護のサポートを活用することで、自宅でも安心して生活を続けることができます。
脳梗塞は、早期発見・早期治療が重要です。特に、FASTチェックで異変に気づいたらすぐに救急車を呼びましょう。 また、退院後の生活では、生活習慣の改善と適切なリハビリが不可欠です。訪問看護を利用すれば、自宅でも安心してリハビリや健康管理を続けることができ、利用者様やご家族の負担を軽減できます。 訪問看護の活用について不安や疑問があれば、お気軽にご相談ください。私たちは、利用者様とご家族が安心して生活できるようサポートいたします。